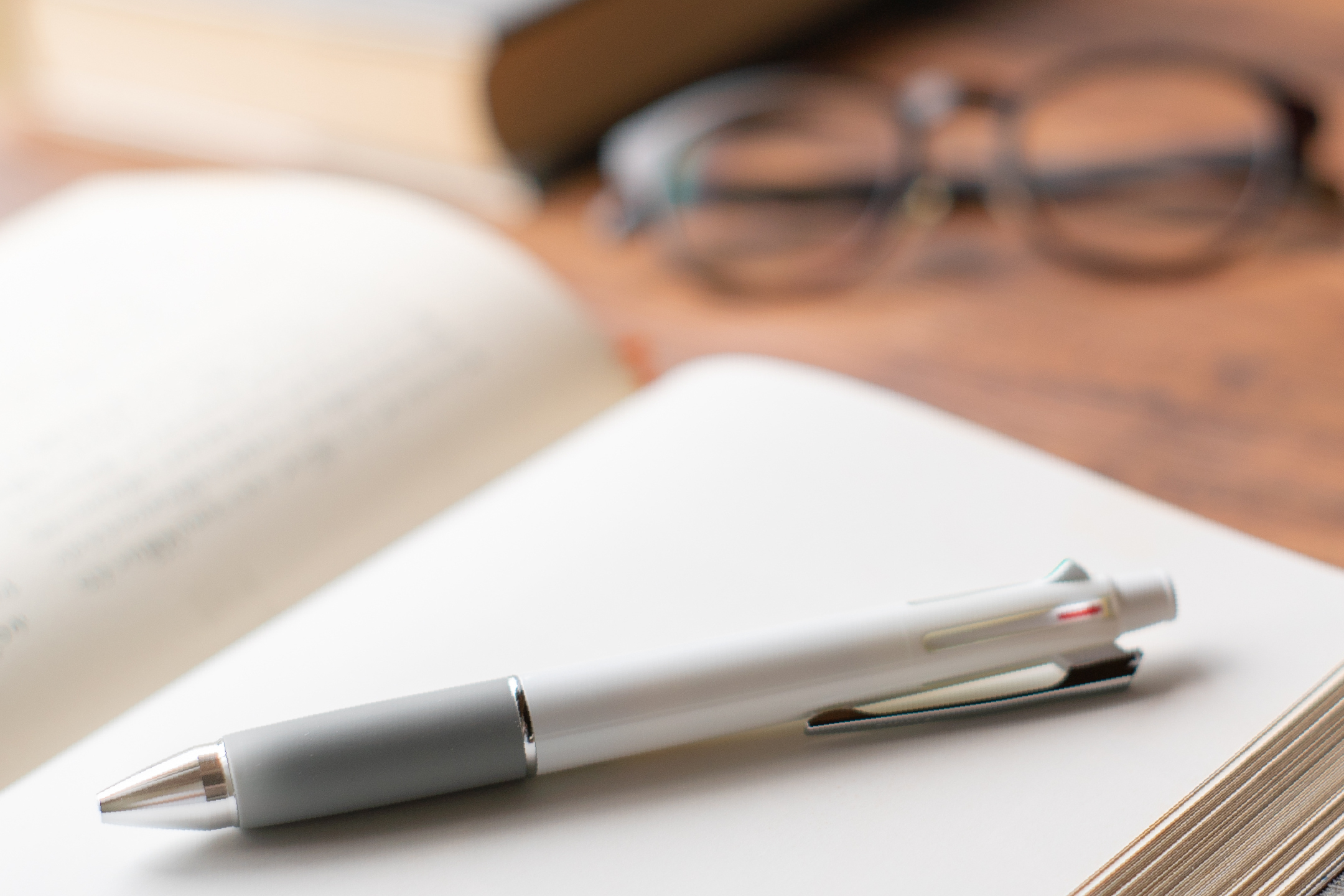今回のコラムでは、印刷やDMにまつわる専門用語を皆さんにご紹介します。
第6弾は[DM編]です。
あ行
アイフロー/視線誘導
印刷物やWEBサイトを見るときの視線の流れを指します。
視線の動きを意識してデザインをすることで、情報が伝わりやすくなります。
アクションデバイス
レスポンスまでのスムーズな導線のことを指します。
目立つ位置にレスポンスツールを設置したり、レスポンス方法をわかりやすく記載するなど、DMを受け取った方が迷わずスムーズにレスポンスできるようにデザインや仕様を工夫します。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
アクティブリスト
顧客リストの中でも直近で自社製品やサービスを購入・契約したなど取引があり、DMなどの広告に好反応が期待できる顧客リストです。
(⇔インアクティブリスト)
アテンション
DMを受け取った方の興味を引くための仕掛けを指します。
具体的にはDMの内容を“自分ごと化”に導くキャッチコピーやキービジュアルなどのことです。
アテンションの有無でDMの開封は大きく左右されるので、必ず掲載することをオススメしています。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
インアクティブリスト
過去に購入・契約といった取引があったが、現在は停止している休眠顧客のリストです。
(⇔アクティブリスト)
エビデンス
商品やサービスの強みの根拠を指します。
スペックで商品の強みを記載しても、どうして優れているのかを明記していないと信用していただけません。
そのため、優れている根拠や具体的な数字を記載することで信用を得ることができます。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
オファー
DMを含む広告によって得られる特典です。割引やプレゼントなどがこれにあたります。
これらはDMの開封や購買行動を促すための仕掛けとして用いられます。
DMの効果を上げる5つの要素の1つであり、効果的なDMを創る11個のコツの1つでもあります。
か行
開封率
一度に送付したDMの内、開封されたDMの割合です。
DMに関する実態調査によると、自分宛てに届いたDMの75.4%は開封・開読されていて、世帯に届く全てのDMでも65.0%が開封・開読されていることから、DMの開封率は高い傾向にあることがわかっています。
「DMメディア実態調査 2022」(一般社団法人日本ダイレクトメール協会)より参照
外部リスト/アウトサイドリスト
自社で保有している顧客データではなく、外部から入手したリストを指します。
新規顧客の開拓などを目的に、名簿業者からリストを購入したり、リストを保有している企業様名義で自社製品やサービスの案内DMを送付するといった利用方法があります。
(⇔ハウスリスト)
カバーレター
手紙や書類、DMに同封される添え状です。
カタログやチラシなどを1つにまとめて発送する際に同封物が何かを記載し、挨拶状を兼ねて送付します。
クリエイティブ
DMに注目してもらうための工夫を指します。
具体的には、コピーやデザイン、ギミックや封入物など仕様も含まれます。
DMを受け取った方に“開けてみたい”、“読んでみたい”、“もっと知りたい”と思わせることがクリエイティブの課題となります。
DMの効果を上げる5つの要素の1つです。
ケーススタディ
商品やサービスの利用前後の変化や効果の記載を指します。
実際に利用することでどのような変化が起こるのか具体的なビフォーアフターを明記することで、商品やサービスを利用してみたいという気持ちを駆り立てます。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
行動喚起率
DMをきっかけに何かしらの行動をとった方の割合です。
DMに関する実態調査によると、DM発送総数の内19.3%が何かしらの行動をとっており、「購入・利用した」が3.0%、「お店に出かけた」が1.3%、「資料を請求した」が2.6%、「会員登録した」が2.1%となり、一方で内容について「インターネットで調べた」が8.4%、「ネット上の掲示板やSNSなどに書き込んだ」が0.4%、「家族・友人・知人との話題にした」が3.2%とDM以外から情報を得たり、逆に情報を広げるような行動も見られています。
「DMメディア実態調査 2022」(一般社団法人日本ダイレクトメール協会)より参照
さ行
実用DM
郵便本来が持つ「連絡を取る」ことを目的としたDMです。
最大の特徴は広告としての機能を持たないという点です。例えば、年賀状や結婚式の招待状といった連絡手段として送るDMがこれにあたります。
アメリカのDM研究家ヘンリー・ホーク氏により分類された、DMの4つのタイプの1つです。
情報DM
即座に注文がくることは想定しないDMです。
例えば、WEBサイトに誘導することを目的としていたり、クーポン券などを付与して来店を促すなど、即座に注文させるのではなく、別の行動へと誘導するためのきっかけを作るDMがこれにあたります。
アメリカのDM研究家ヘンリー・ホーク氏により分類された、DMの4つのタイプの1つです。
スペック
商品やサービスの強みを指します。
他の商品との違いやこの商品にしかない特長などを明確に記載することで、商品の良さをアピールします。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
セグメント
既存顧客や見込み客を、年齢や居住エリアなどの基本属性や購入履歴などさまざまな条件で細分化することを指します。
条件を定めて分類することで、DMのターゲットや広告内容を絞り込むことができ、より効率的な販促を行うことができます。
説得DM
注文・お問い合わせといった行動を促すことを目的とするDMです。
注文用紙や申込書などのレスポンスツールが備わっていて、届いた時点ですぐに商品の注文やお問い合わせができるDMがこれにあたります。
アメリカのDM研究家ヘンリー・ホーク氏により分類された、DMの4つのタイプの1つです。
全日本DM大賞
DMを「戦略性」「クリエイティブ」「実施効果」の三軸で評価する、日本郵便株式会社主催、日本最大のDMアワードです。
想起DM
特定のイメージや名称を定着させることを目的としたDMです。
企業や商品のブランディングや、ユーザーに忘れられないように定期的に情報を発信するDMがこれにあたります。
情報DM、説得DM、実用DMでもイメージや名称の定着ができるため、分類が難しいのも特徴です。
アメリカのDM研究家ヘンリー・ホーク氏により分類された、DMの4つのタイプの1つです。
た行
ターゲット
DMの発送先を指します。
DMを受け取る方の人物像を明確にし、送り先を絞り込み、ターゲットに合った商材のDMを適切に送ることが大切です。
受け取った方にとって全く関係のない内容のDMを送ってしまった場合、そのDMはただのゴミとなってしまいます。
DMの効果を上げる5つの要素の1つです。
ターゲティング広告
特定の条件に合致するユーザーを絞り込み、その条件に適した広告を発信する方法です。
条件には性別や年齢、趣味や世帯といった内容で絞り込む方法や、居住エリアで絞り込む方法など、さまざまな選択肢と組み合わせがあります。
タイミング
DMを発送する時期を指します。
DMに掲載されている商品の季節感、イベントの開催時期などを意識して発送することはもちろん、例えば、前回購入された商品が使い終わる頃を見越して通販DMを送ったり、契約期間の更新が近づいている方にアナウンスDMを送るなど、受け取る方に合わせた時期にDMを発送することもタイミングにおいて重要なポイントとなります。
DMの効果を上げる5つの要素の1つです。
テスティモニアル
商品やサービスの強みの根拠に説得力を持たせるための内容を指します。
専門家や著名人など第三者の意見を記載することで、エビデンスとして記載した根拠により説得力の深みを増すことができます。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
ドアオープナー
DMの開封を促す仕掛けです。
仕掛けにはいろいろな種類があり、特別な開封の仕方や変わった形、型抜きをして中身を少し見せる、サンプル品など手触りのあるものや立体的なものを同封するなどが挙げられます。
は行
パーソナライズドDM
顧客一人ひとりに合わせて掲載内容をカスタマイズしたDMのことです。
例えば、購入履歴から類似商品の紹介を載せたり、居住エリアに合わせて最寄りの店舗情報を可変で載せたりすることで、その人にあった情報をピンポイントで届けることができます。
ハウスリスト
企業ごとに独自に保有している顧客リストで、自社製品やサービスの利用者や会員をリスト化したものです。
その中でも動きのあるアクティブリストや休眠顧客のインアクティブリストといったように顧客リストを分類している企業もあります。
(⇔外部リスト)
フォローアップDM/リマインドDM
DMで一度アプローチをした方に向けて、再度同じ目的のDMを送ること。
最初のDMを思い出すきっかけ作りや行動喚起に役立てます。
ブランド
DMに掲載されている企業名やロゴを指します。
DMがどこから送られてきたのかがきちんと伝わるように、企業名やロゴをしっかりと掲載します。
企業名などが明記されていることで、企業や商品の認知拡大やDMそのものの信用性にも繋がります。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
プロミス
開発者や販売担当者の声を指します。
自分たちが売り出している商品やサービスにどんな魅力が詰まっていて、どれだけ自信があるのか、自分たちの目線から評価した情報を掲載します。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
ベネフィット
DMを受け取った方のどんなニーズを満たせるのかを記載した内容を指します。
よくメリットと混合されがちですが、例えば、漢字ドリルをやることで漢字を覚えられるのはメリットで、それによってテストの点数が上がることがベネフィットとなります。
メリットによって得られる恩恵を記載することが重要です。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
ま行
マッチング
複数の可変した印刷物を1つにする作業です。
例えば、封筒に宛名が印字されていて、中身の申込書やフライヤーなどにも個別の情報が印刷されている場合、それぞれを照合して間違いが無いように封入するといった作業があります。
宛名違いや封入違いを防がなければならないため、とても慎重かつ重要な作業となります。
や行
ユーザーボイス
実際に商品やサービスを利用しているユーザーの声を指します。
実際に利用している人の感想や体験談を掲載することで、DMを見ている人を共感させ、より商品への興味を引くことができます。
効果的なDMを創る11個のコツの1つです。
ら行
ラベリング
DMに宛名情報が印字されたシール(宛名シール)を貼る作業です。
中面や封入物に個別の情報が印刷されている場合はマッチング作業が必要となります。
リーチ/到達率
発送されたDMの内、実際に宛先に到着した割合のことを指します。
例えば1,000通のDMを送った場合に、その内900通が宛先に到達し、残りの100通が配達ミスや宛先不明などの理由で戻ってきた場合、到達率は90%で不着率が10%となります。
レスポンスツール/オーダーフォーム
お問い合わせや注文といった返信を目的としたツールを指します。
商用DMのほとんどには返信用のFAX用紙やハガキが同封されていたり、QRコードでWEBに誘導したり、電話やメールアドレスといった返信先の情報が記載されています。
ガリバーではレスポンスツールに事前にお客様情報などを印字する事が可能です。返信時の記入の手間を減らすことでレスポンスに繋がりやすくなります。
DMの効果を上げる5つの要素の1つです。
レスポンス率
お問い合わせや注文といったDMの目的に沿った返信数を到達数で割った値です。
レスポンス率の計算は「返信数÷到達数×100」となります。
例えば、1,000通のDMを送った内、900通が到達し、180通からレスポンスがあった場合、「180÷900×100=20%」でレスポンス率は20%となります。
最後に
・DMの効果を上げる5つの要素
・効果的なDMを創る11個のコツ
・DMの4つのタイプ
これらについては、それぞれ個別に紹介した記事があります。
そちらもぜひご覧ください。
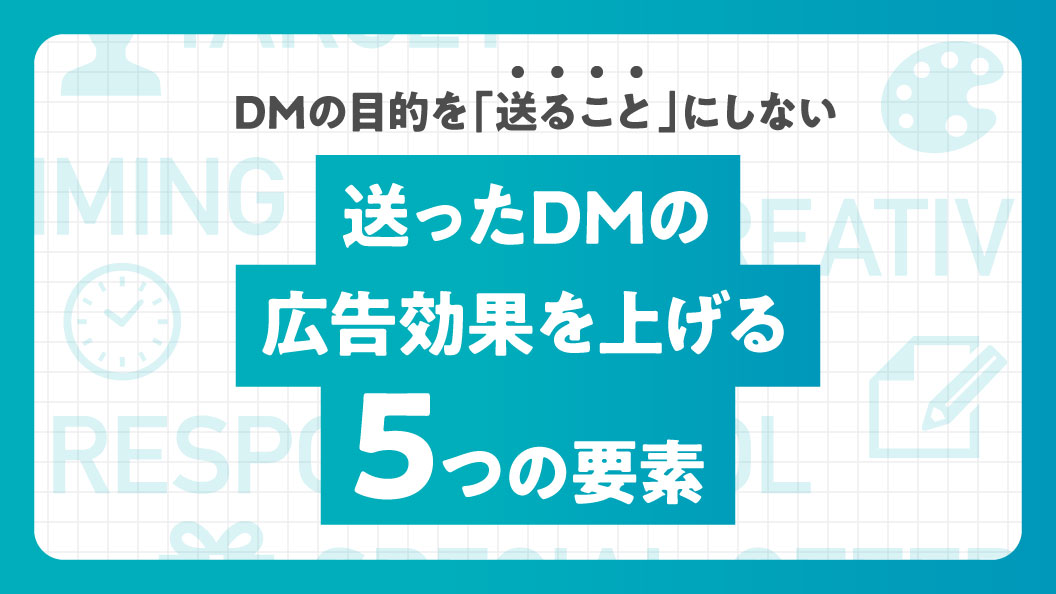
DMの目的を「送ること」にしない 送ったDMの広告効果を上げる5つの要素> 詳細はこちら
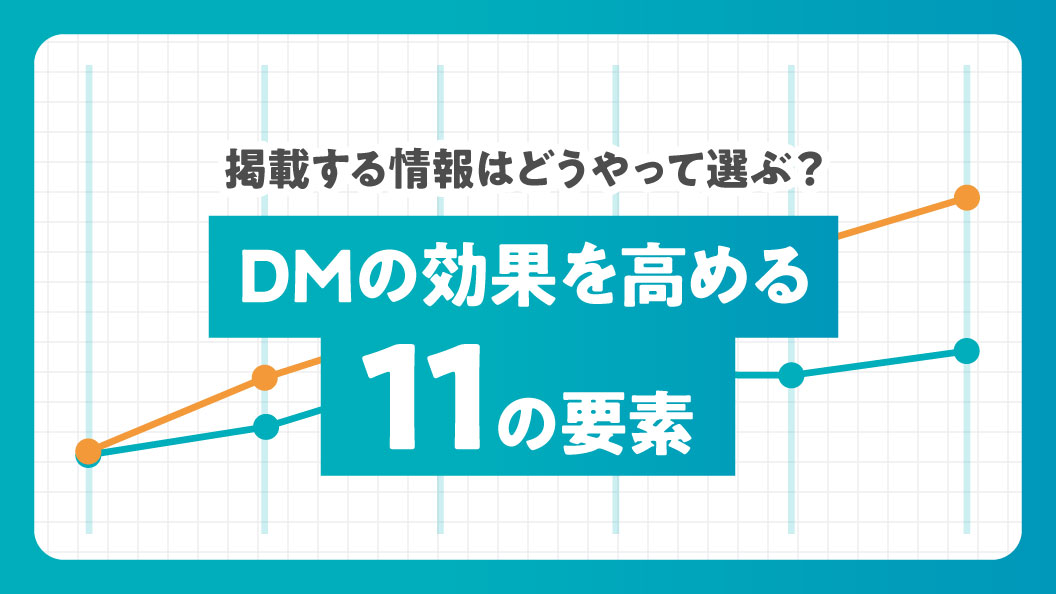
掲載する情報はどうやって選ぶ? DMの効果を高める11の要素> 詳細はこちら
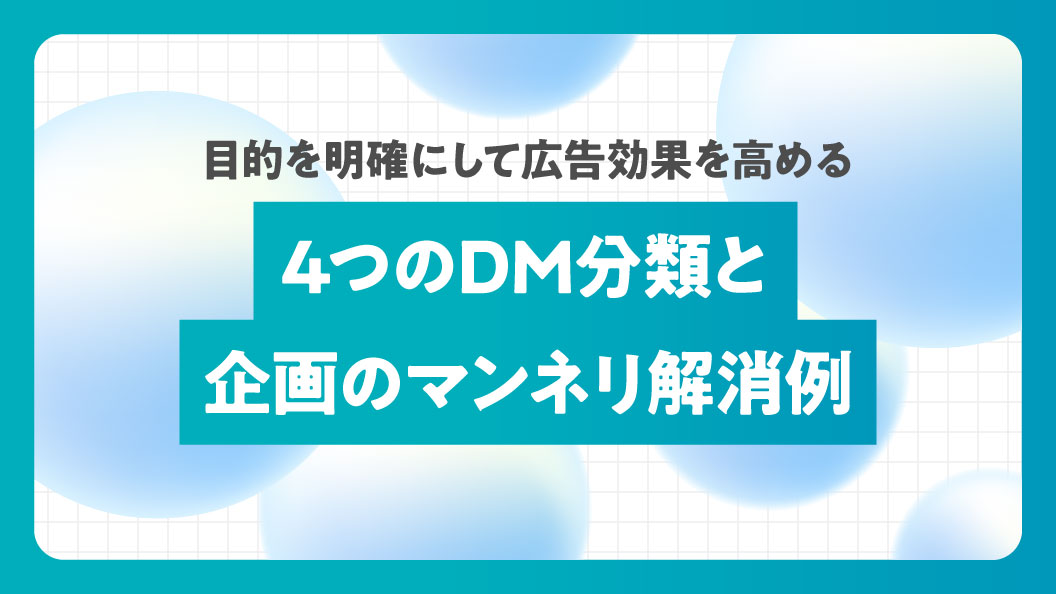
目的を明確にして広告効果を高める 4つのDM分類と企画のマンネリ解消例> 詳細はこちら
ガリバーはDMの印刷・発送にとどまらず企画からお客様を全面サポートしています。
この記事の詳細やDMサンプル、成功事例などお気軽にお問い合わせください。
![知っていて損なし!印刷用語・DM用語集 [DM編]](https://images.microcms-assets.io/assets/f554d0c1b00a4cc7b54740259fcd00e7/20e1aef0eef046159e8ae003f58788d2/52.eye-catcher.jpg)

![知っていて損なし!印刷用語・DM用語集 [校正編]](https://images.microcms-assets.io/assets/f554d0c1b00a4cc7b54740259fcd00e7/14d0018505d746e5b9f542f9142efd99/40.eye-catcher.jpg)
![知っていて損なし!印刷用語・DM用語集 [製版/印刷編]](https://images.microcms-assets.io/assets/f554d0c1b00a4cc7b54740259fcd00e7/55a9f123ed9545c49d415730c3caad89/41.eye-catcher.jpg)
![知っていて損なし!印刷用語・DM用語集 [加工編]](https://images.microcms-assets.io/assets/f554d0c1b00a4cc7b54740259fcd00e7/a8f0936ff9a1478294f72f8d831b33c7/42.eye-catcher.jpg)
![知っていて損なし!印刷用語・DM用語集 [印字/郵便編]](https://images.microcms-assets.io/assets/f554d0c1b00a4cc7b54740259fcd00e7/a0ddc2400e0f4f41a3c624104c80a9b9/50.eye-catcher.jpg)